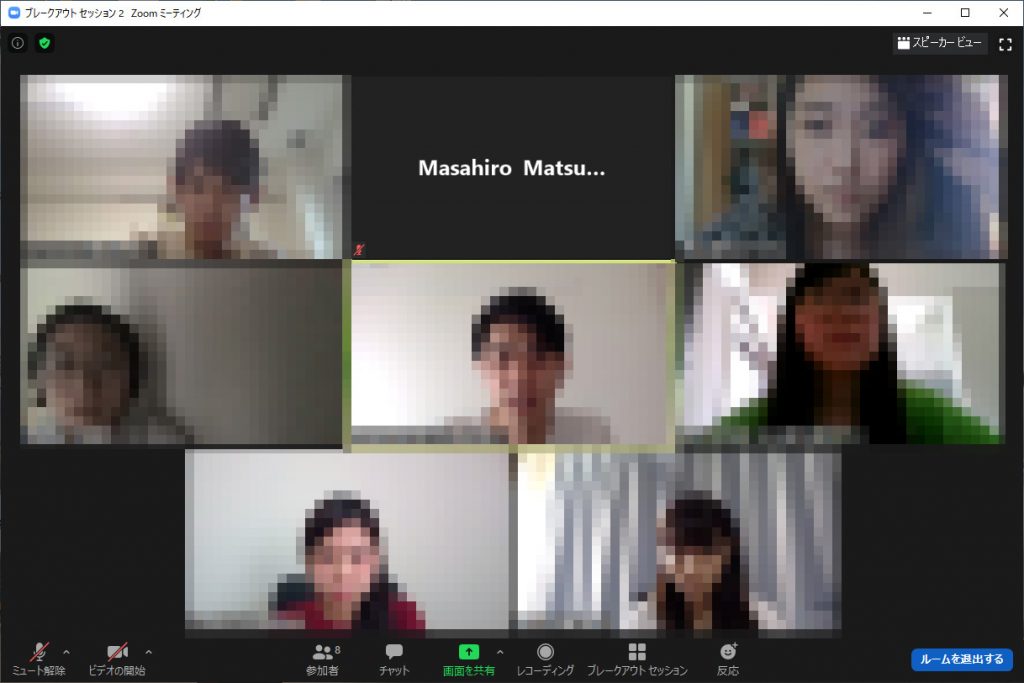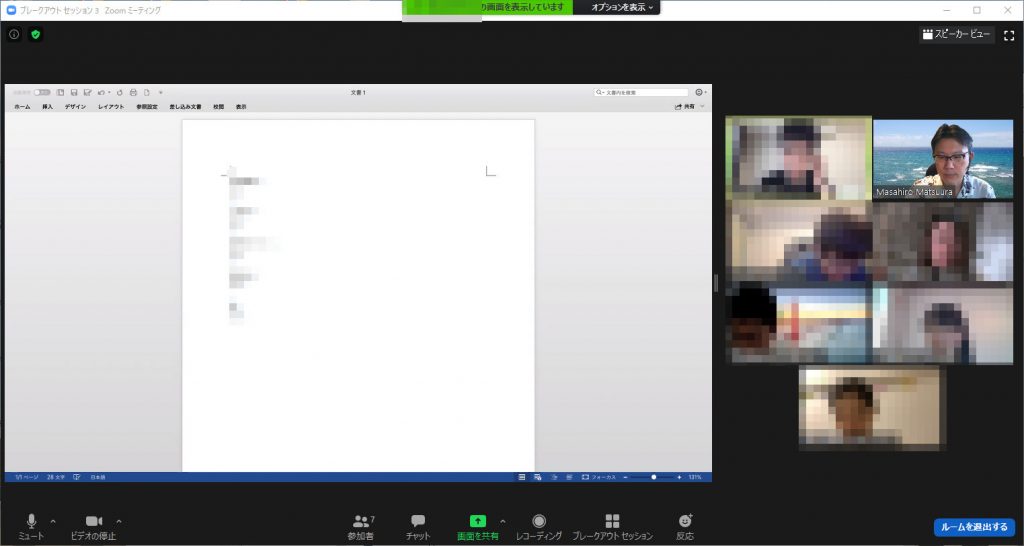2020年6月9日
いやほんと、今日はビックリしましたよ。
小職が東大の公共政策大学院で10年以上担当している科目「交渉と合意」。交渉分析の基礎と政策形成への応用をお話ししているのですが、今日は6者間での公共事業に関する合意形成模擬交渉。
「ハーボコ」という教材で、小職のMITの師匠が制作した教材なんですが、利害調整の論点が5つもあって、しかも各役割の利害が複雑に入り組んでいるのに、授業時間内の1時間半で合意形成を図る必要があり、さらにちょっとしたトリックも仕組まれていて・・・
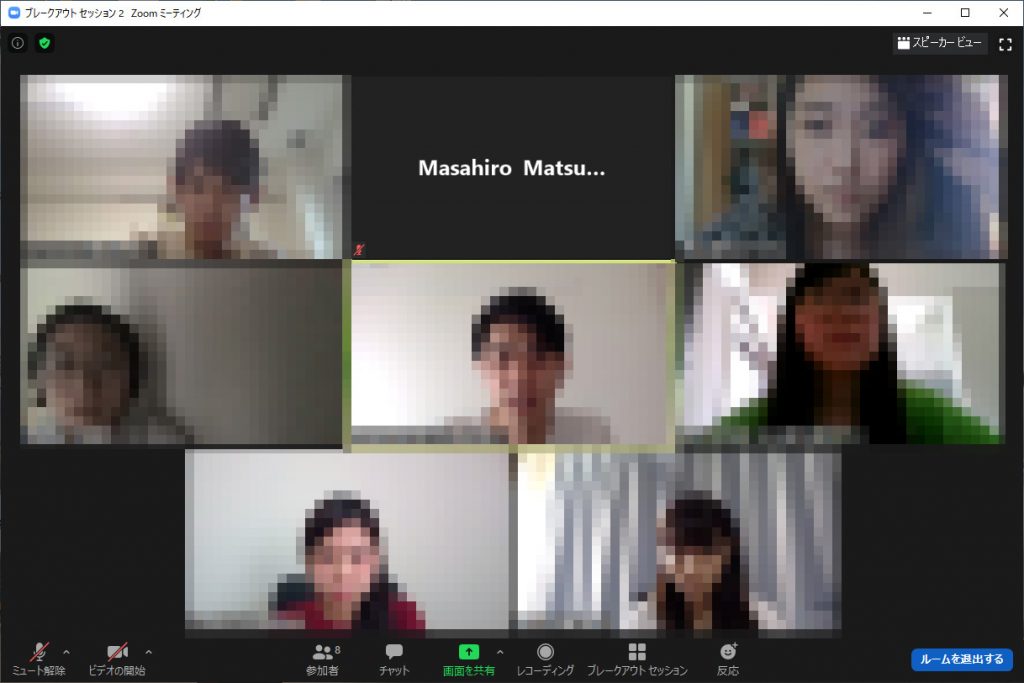
という、なかなかスリリングな演習です。この講義を受講した修了生のみなさんのなかには、この演習のことを忘れずに覚えている人も多いと思います。
で、何がビックリしたかといえば、今日はオンラインでやったわけです。
ZOOMでブレークアウトルーム機能をつかって原則6人1組(3グループ)に分かれて演習に参加してもらったんですね。
オンラインだからコミュニケーションがうまくとれないだろうなぁ、6者間なんて話し合いになるのかなぁ、と、やってみるまではドキドキでした。実際、ブレークアウトルーム機能が想定通り機能せず、講義開始直後にいったん全員にログオフしてもらって再度立ち上げなおすといったトラブルに見舞われたほど。
ですが、3グループのうち、2グループがなんと1時間程度で6者間合意に到達してしまったのです!
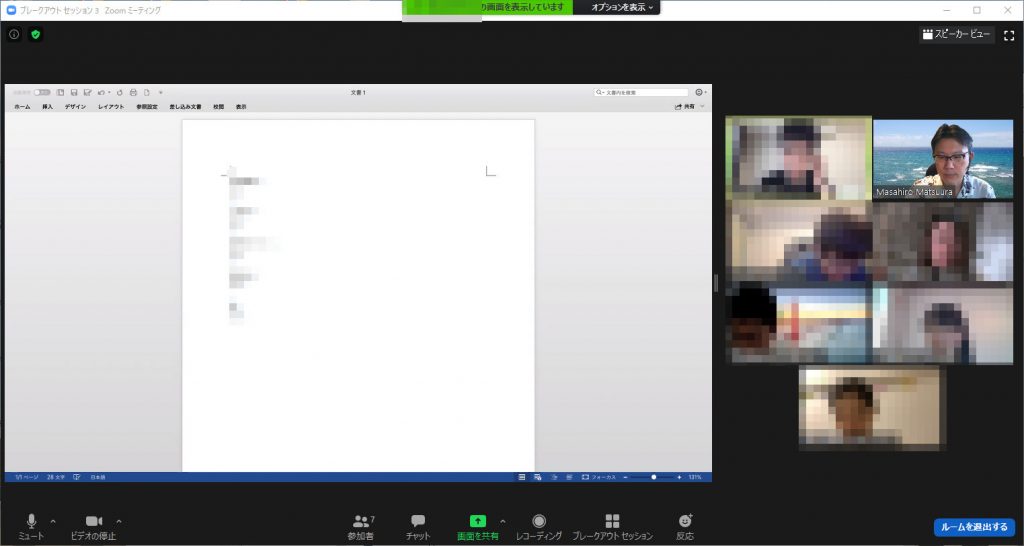
通常であれば1時間半かかる演習が2/3の時間で合意に達してしまう、しかも例外的ではなく3事例のうち2事例、しかも覗き見していた感じ、特になにか「凄い」進行が行われていたような感じではないグループで、短時間で合意形成成功とは・・・。
これはZOOMというかテレビ会議の可能性を示唆しているような気がします。いちどnegotiation journalあたりで既往研究がないかどうかチェックしたいのですが、マルチステークホルダーの合意形成をオンライン会議にすると、時間の効率化が図られるのかも。とはいえ逆に、議論の質がどうだったかの検証も必要なんですがね。
コロナ禍は多者間交渉を大きく変えるトリガーなのかもしれない、と思うと鳥肌ザワザワした午後でした。
2017年11月29日
先日、社会選択理論の本を読んでいたら、equilibrium selectionという言葉がでてきました。ふむふむ、確かに複数の均衡解が存在するとき、どれを選択するのかを考える必要がありますね。
でも現実の社会では、ある程度の均衡解がすでに実現しているわけです。ある一定の環境下でみんながそれなりに合理的に行動していて、行動がそんなに変化しないのであれば、それは均衡解が実現していると言ってもよいのでしょう。
自分は最近、トランジション・マネジメントというお題の下、どのように社会経済システムの構造改革を実現し、人々の行動を変えることができるのかを、実践的に調べていますが、これもまさにある意味、とある均衡解から別の均衡解へといかに移動するか、という問題ととらえることができそうです。
たとえば、化石燃料に依存する現在の社会ですが、これはこれで極めて合理的にできていて、システムの最適化がかなり図られているのではないでしょうか。たとえば、ガソリン価格が高くなればハイブリッドカーが売れるわけです。しかし、そもそも化石燃料に依存しない、いわゆる「脱炭素」社会へ移行しないと、気候変動や資源枯渇の問題にいつか直面するという危機感もあり、全く違う新たな均衡解へと移行する必要があるといわれています(その必要性がない、という反論もありそうですが)。

図を描いてみましたが、AとBという均衡解がわかってて、わたしたちの社会がAであるとき、Bの社会へと移行したほうがよいことは判ります。しかし、いきなり不連続で瞬間的にBへと移行できるのではなく、途中で「A地点からB地点まで」((c)ザ・ぼんち)の経過を辿っていく必要があるわけです。Bの方向へと移動しようか・・・と少しだけ移動してみても、いややっぱしAの均衡解のほうが(ちょっと移動した状態よりは)いいよね、ってことで、やっぱしAに元戻りしちゃうわけです。均衡解というのは起き上がり小法師のようなもので、自己安定化メカニズムがあるからこそ、均衡解なわけです。そうすると、いまの私たちの社会はいわば「蟻地獄」で、抜け出すことができないのかもしれません。
だからこそ革命論みたいなものが20世紀には流行して、不連続的で瞬間的に移行しなければ社会は変わらない、ということだったのかと思いますが、それは無理じゃない?というのが現在のモードかと思います。とはいえ、社会経済システムの変革が人類の持続可能性維持のために避けられないのであれば、いかに「A地点からB地点まで」の移行を実現するのか、それがトランジション・マネジメントの挑戦なんじゃないかと思います。