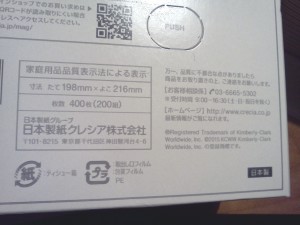2016年4月22日
こんにちは、明治大学の松浦です。明大に転職して以来初のブログ投稿です。
ということで、通勤ルートが変わりまして、南北線から後楽園駅で乗り換えて、神保町駅か御茶ノ水駅を使うことになりました。研究室により近い神保町駅へ行くのがデフォルトで、後楽園駅で都営三田線に乗り換え(※後楽園駅と春日駅は実質同じ駅)なのですが、あまり利用者がいないのか、けっこう、スムーズな乗り換えです。ただし三田線は混みすぎ。
それはおいといて、キャンパスの御茶ノ水駅側のほうで用事があるときは、御茶ノ水駅を使うこともあるのですが、南北線から丸の内線の乗り換えはほんと、苦行です。というのも比較的新しい南北線は地下奥深く、それに比べて丸の内線は地上に露出してて高架になっているので、地下4階から地上2階まで移動しなきゃいけないイメージです。後楽園って実は本郷の丘と護国寺のほうの丘との谷あいに位置するんですね。
で、乗り換えですが、もちろんエスカレーターが重装備されているので、時間さえかければ、(メンタルはともかく)フィジカルに疲れることはありません。しかし、僕が朝の通勤時間帯にこの経路を使ってしまうと、フィジカルにも消耗します。なぜか。
エスカレーターで歩く(登る)人は右側、止まる人は左側という不文律は人口に膾炙したところですが、後楽園駅のエスカレーター(特に地下3階から地下1階までの長いやつ)を登るのはクソ疲れるのでみんな左側に乗ろうとします。しかしエスカレーターの処理能力以上に通勤客が多いので、左側に乗ろうとする人たちが待機して、踊り場やプラットフォームに滞留します。しかし朝のカッタルい通勤時間から右側を駆け登ろうとする武井壮的肉体派は少ないので、右側はかなり空いているのです。かといって、たまに登る人はいるので、右側で止まるのもルール違反な気がします。なので、僕は渋滞嫌いなので、混雑時はハァハァ言いながら地上2階までエスカレーターを登ることにしています。
まぁそんな不都合が起きているわけです。
こういう問題はどこでもあるようですね。ということで、ロンドンの地下鉄は、片側を歩く人にあけておく(ロンドンは左側らしい)のを止めさせるようにしたそうです。いちおう彼らの試算(ホルボーン駅のエスカレーター)によれば、左を歩く人用に空けると81.25人/分の処理能力だそうですが、両側を止まって使うと112.5人/分の処理能力だそうです。このホルボーン駅、どうやら後楽園と同じで距離が長い(高低差23.41m)だそうで、やはり歩く人が少なくて、乗り場に滞留しちゃってたそうです。
The tube at a standstill: why TfL stopped people walking up the escalators| The Guardian
ということで海外事例大好きな日本のお役所ですもの、国土交通省はぜひこのアイディアを社会実験として東京メトロと協力して導入してほしいなぁ、と思う次第。夏の概算要求の球出しに向けてつかってみたらどうでしょう?
2015年12月30日
タイトル見てエロい内容だと思いました?
安心してください、エロくないです(ゴメンナサイ)。
先日、食卓で使うティッシュを間違えて2箱出してしまったのです。いずれもスコッティのぱっと見、同じ箱なのですが・・・なんとなく眺めていたところ・・・

大きさがぜんぜん違うじゃん!
幅はほぼ同じですが、高さがかなり違います。「安売用に中身減らしてんじゃねぇの?」と疑ったものの、いずれも400枚(200組)との表記あり。
どうなってんだろ?とよく見てみると、片方の裏面には「(c) 2011 KCWW Kimberly-Clark Worldwide…」、もう片方には「(c) 2015 KCWW Kimberly-Clark Worldwide… 」と書いてある。
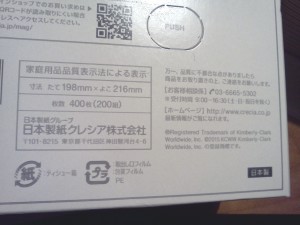
なるほど、どうやら片方は、震災後のどこかで備蓄用に買っておいたティッシュだったらしい。もう片方は最近買ったティッシュ、ということらしい。もちろん、最近買ったほうがコンパクト。
ということでサイズ(外寸)を計測してみると・・・
2011(?)版:
W 236 x D 117 x H 55 = 1518660 mm^2
2015版:
W 227 x D 117 x H 45 = 1195155 mm^2
ってことで容積にして21%の減容!
すごいですね。輸送にかかるコスト、CO2の排出、その他諸々をずいぶん節約できてますね。
こういうのこそイノベーションってやつなんじゃないか、ってことで、「ティッシュ・イノベーション!」って叫びたくなってしまいました。
もちろん、「イノベーションなら、そもそも木質パルプを使わなくてもいい、あるいは再利用できるようにするくらいの革新が必要なんだ!」と力説される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、何はともあれ、わずか数年で20%の減容っていう企業努力は、イノベーション!と称えてもいいんじゃないかなぁ、と思うわけでして。
2015年12月16日
小職担当の「海洋科学技術政策論」講義では、毎年、銚子(千葉県)と神栖(茨城県)の洋上風力発電施設の見学に伺わせていただいています。今年は昨日12月15日に実施。12月だというのに太陽がふり注ぐ暖かい1日で、屋外での見学には最高の日和でした。
しおさい1号に乗って銚子駅集合、すぐに外川漁港までバスで移動です。外川漁港では、ちょうど釣りの漁船が帰港してくるところで、活気ある様子でした。

さっそく、漁船(釣り船)に乗り込んで、視察に出発です。

銚子の洋上風車は、沖合3kmほどのところにあります。この日は定期点検で、風車は廻っていませんでした。

台風のせいで、送電ケーブルを海中に下ろしていく箇所(下写真の左側)が破損したそうです。やはり波の破砕力は大きいんですね。
ということで写真中央に見えるように、基礎にベッタリと這わせるような配線に修正されたとのこと。これも「実証実験」の強みですね。

この日は波高1.3mと、まぁまぁ穏やかな感じがしましたが、下の写真にうつっている船で判るように、けっこうな揺れでした。

最後に陸上の変電施設にも伺いました。隣は銚子マリーナ海水浴場といって、きれいで長閑な砂浜です。ここからでも沖の風車が見えます。夏は混雑するようですね。

次に1時間弱、バスで移動し、神栖のウィンドパワー(小松崎さん)の風車の見学にいきました。
神栖までの道のりでは、バスの運転手さんが気をきかせてくれたのか、沿岸の風車街道を走ってくれました。

沿岸から見ても「洋上」って感じがしませんが・・・

突堤に出て眺めると、ちゃんと洋上ってことが判ります。
ちなみに(第1期は)陸上から施工されたのでFIT上は陸上の風車と同じ単価だそうです。

今日のベストショット。神栖で導入されている日立/富士重の2MWダウンウインド型。
ウィンドパワーさんのスゴいなぁ、と思うところが、地元経済への思いが強く、国産・茨城産の風車を導入していること。

今度の鹿島港ウィンドファーム(まずは20基建てるそうです)では5MWを導入されるそうで、鹿島港の南堤付近の陸上に実証試験機が建っていました(まだ稼動してないようです)。