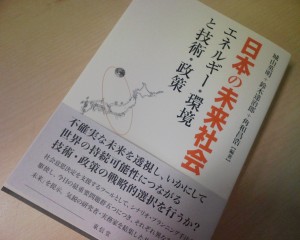2010年6月4日
RISTEX-WSのメモ
社会技術研究開発事業 新規研究開発領域 事前検討のためのワークショップ
http://www.ristex.jp/aboutus/enterprize/network/100607.html
このイベントに出るのですが、事前にレジュメを、ということだったのでつくってみました。ustで放映されるそうなので、こちらにも掲載しときます。
社会技術研究開発事業 新規研究開発領域の事前検討
話題提供のメモ
Q:社会における解決すべき問題、あるいは、取り組みや支援が不足している課題には、どのようなものがあるか。
(科技)社会的合意形成における専門知の役割に関する研究と実践
科学的な課題が関わる合意形成の現場では、専門家としての言説と、利害関係者としての言説をある程度仕分ける必要がある。米国では共同事実確認(joint fact-finding)という枠組みが次第に形成されつつあるが、日本でも同様の枠組みを考える必要がある。
(一般・科技)合意形成を支援する第三者組織
特に対立状況にある場合には当事者による自主的な合意形成は難しい。社会的見地からプロセス運営を果たせる第三者が重要となる。米国ではフリーランス含め専門家集団が多数存在する(CONCUR、CBI、RESOLVE、CDRなど)。日本はまだ萌芽期。
(一般)合意形成に関する学際的研究体制
合意形成についての研究(とその成果を引き継ぐ実践)には高い学際性が要求されるが、トップダウンでCoEが確立されなければ、研究者間の利害対立により協働は難しいのではないか。たとえばHarvardのProgram on Negotiationは交渉(と合意形成)に関する学際研究の受け皿として有効に機能している。
(一般)合意形成(交渉)に関する基本的枠組みの教育
合意形成の方法論、枠組みはまさに「社会技術」であるとともに、汎用性が高いものであるから、一般への教育が重要である。たとえば、米国の専門職大学院では「交渉学」教育が当然のように行われている(ただし日本でも同様の傾向が形成されつつある)。
Q:その中で、当センターの研究開発領域として取り組むべきテーマにはどのようなものがあるか。(また、その研究開発成果の普及や展開の可能性の有無、成果の受け手のイメージなど)
・社会的(参加型)意思決定と科学技術(専門知)の接続についての実践的研究
・CoEあるいは第三者組織立ち上げにつながる実践的研究
米国ではHewlett Foundationが過去20年程度継続的に支援してきた
・合意形成論全般に関する研究