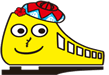2023年1月6日
Z世代、沖縄行きたくても運転が壁 ドライブ消極派は旅行敬遠 レンタカー観光に課題 若者意識調査
いまの若い子たちは、観光地をあくせくと巡回する高齢者と違って、ノンビリと滞在型観光を楽しめる世代だろうから、リゾートまでの交通手段がちゃんとしていればいいんだろうな。そう考えれば、空港から各拠点まで高速バスを増やせばいいし、地区内の主要スポットを巡回するバスを走らせればいい。レンタル電動自転車も増やして、走行環境を整備すればなおよし、だろう。現在のハワイ・ワイキキみたいな観光交通のすがたに変化するだけではないか。
とはいえ、高速バスだと輸送力が限られるだろうから・・・もしかしたら鉄軌道を本当に整備する時が来たのかもしれない。
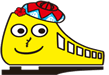
沖縄鉄軌道計画
計画検討に末席に連ならせていただいた者としては、確かにそろそろ、整備を考えてほしいところ。
空港から恩納村まで40分くらいで走る電車が15分に1本くらいの頻度で走っていて、駅までホテルが送迎してくれる仕組みができれば、レンタカーがなくても全く問題ないだろう。
さて、未来に向けた投資は始まるのだろうか?
2023年1月4日
米国がバイデン政権になって2年が経ち、脱炭素の動きが当然のように加速(というか遅れを取り戻)し始めておりますが、インフレ抑制法(IRA)に基づく再エネ発電と水素生産に対する税額控除導入がゲームチェンジャーになりそうとのこと。
CAN THE INFLATION REDUCTION ACT UNLOCK A GREEN HYDROGEN ECONOMY?
再エネ発電はkWhあたり2.6セント、水素生産は1kgあたり3ドルの税額控除を2023年から10年間受けられるようになるはず、のようです。FITに比べればたかが知れた金額かもしれませんが、ややこしい手続きなく、単純にkWhあたりで確実に税額控除を受けられるのであれば、キャッシュフローの予測もしやすいですし、技術もその時点・場所で最適なものを使えばよいので、ガバナンス・メカニズムとしては雑駁なようでいて実は投資誘発の効果が大きそうです。
また再エネ発電と水素生産を組み合わせる、つまり風車の下で水素生産を行う事業を始めたら、両方の便益が受けられるそうです。なので、いわゆる「グリーン水素」への転換が進むのではないかという話にもなってきているそう。自動車はBEV化の方向へと舵が切られつつあり、FCVはパッとしなくなってきましたが、工業生産やメタネーションなど水素はいろいろな場面で必要になるでしょうし、ちゃんとそういうところにも大胆に投資できる米国というのはすごいなぁ・・・と日本で指をくわえて見ているしかないのはツラいですね。
2022年9月8日
どこの政府も気候変動対策に原発を使わざるを得ない状況になってきているようであります。
California governor signs bill to keep last reactors running
https://abcnews.go.com/Technology/wireStory/california-governor-signs-bill-reactors-running-89248052
カリフォルニアでは2025年までの廃炉を決めていたディアブロキャニオン原発を2030年まで運転延長する法案が通過し、知事が署名したとのこと。気候変動対策の法案のパッケージの一つだそうです。民主党内でもこれはかなり揉めたようですが、結局、ほぼ全員一致で法案は通過したそうな。
日本も原発再稼働という話になってきています。2011年のメルトダウン以降、再エネ導入は一部の太陽光以外は遅々として進まず、政府は原発をベースロードだと言いながらもほとんど再稼働できず、結局、老朽化した火力に頼って誤魔化してきたので、いま脱炭素しようとしたら短期的には原発しか選択肢がないという状況なんでしょうね。そんな政権が長期にわたって選挙で当選してきたのですからこの国の自業自得といえば自業自得。
とはいえ、少なくとも日本の過去10年よりは再エネ導入に積極的だったと思しきカリフォルニアでさえこんな状況なので、ロシアの乱暴狼藉の影響も加わって、「現実的」というか、リスクがあっても使えるものを使わざるを得ない状況に世界が直面しているのでしょう。
この局面で、目前の課題解決で手一杯になるのか、それに加えて2030年から先のことも考えた準備を進められるのか、その違いが国力の違いとなって10年後に表出するのでしょう。