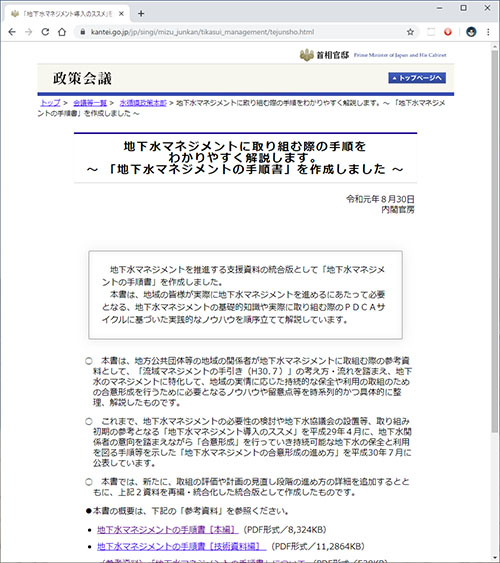2022年9月6日
東日本大震災の前から洋上風力発電の立地に興味があって、研究というか、ただの興味というか、初期の事例を10年以上、つぶさに観察させていただく機会を得てきました。
なかなか「論文」にならんので、科研費の報告書に小品を提出するくらいしかできてない自分が情けないわけですが…
https://www.mmatsuura.com/research/offshore-wind.html
初期の事例って、実証事業ということで、民間企業の担当者も半ば研究者のようなタイプの人が多く、ガツガツしてないわけです。ということで、可能性がありそうな地域に話にいくときも、金儲けのことはあまり考えてなくて、「まずはこの海で風車をやらせてもらえませんか?一緒にやりませんか?」、というご挨拶から始まってたんですね。まずは調査をさせていただくということで、どんな漁業をどんなところでやっているのかなどを、丁寧に話を聞いたうえで、そこから風車を建てるかどうか、建てるならどこに建てさせてもらうかをご相談しましょう、という話になるわけです。地元が絶対NOであれば、別の場所に移ればよいわけですし。
先日、青森の洋上風力の話で日経新聞の取材を受けたのですが、どうやら県庁が、予定地の目の前にある漁協の了解を取ったものの、離れたところにある漁協に話をせずに「協議会」などという組織を立ち上げてしまったものだから、トラブっているようなんですよね。

「どうしてひとこと、話を通しておかないのかなぁ?」と、とても不思議な気分になるわけです。忙しくてそこまで手が回らなかった、というの言い訳も理解できなくはないですが、最初に一度話をしておけば、あとはスムーズに進むことも多いので、とりあえず水産課、試験場、県漁連などを通じて調査して、ご挨拶しておけばよいだけのことなのですが。水産資源って、沖に行けば行くほど、誰が漁獲しているかわからなくなるし、さらに魚は回遊するので、漁場ではない場所だって産卵の場所かもしれず、よくよく調べてから話を進めないといけないので。
国のガイドラインとやらには、「協議会」を立ち上げてといったことが書いてあるわけですが、きちんとステークホルダーを探索するという、あたりまえのことは書いてないのかもしれませんね。ガイドラインの策定に自分は全く関わってないので、知らんけど、ってやつですが。
2021年9月14日
お金って、たとえば1円玉と10円玉を一枚ずつ出せば、11円として受け取ってもらえますよね。硬貨も紙幣も、基本的には1円は1円として無差別に扱うのが一般的なルールです。
同じようなルールが、エネルギー政策や気候変動政策にも、適用されているような気がしなくもないです。1kWhと1kWhを足せば2kWhだし、1トンのCO2と1トンのCO2を合わせれば2トンのCO2。もちろん電気は貯蔵が難しいので、その時その時の需要に合わせて発電しないといけませんが、ある時点で需要と供給が一致するように、需要の足し算と供給の足し算の帳尻が合えばそれでよいのでしょう。
じゃぁ、人口問題はどうでしょう?1人と1人を足せば2人です。ってことは人間も、電力やCO2と同じく、カウントして、帳尻合わせできるものでしょうか?
人間って一人一人、かなり違った存在ですよね。1人足らなければ、1人増やせばいいとは限りません。引っ越し屋さんで1人不足だからといって、90歳の爺さんを1人連れてきても、問題は解決しないでしょう。
何を言いたいかというと、人間の場合、ひとりひとりに特徴があるので、「数」を揃えるだけではあまり意味がないかもしれないということです。
じゃぁ電力やCO2はどうかといえば…たとえば、自宅のコンセントで1kWh使ったとき、その1kWhがどこでつくられて、どうやって運ばれてきた電力なのか、大多数の人は意識しないでしょう。きちんと電子レンジを動かしたり、エアコンを動かしさえしてくれれば、1kWhはどんな1kWhであったとしても、実用的には、気にならないわけです。CO2もまたしかり。温室効果を減らしたければ、誰のどんな活動でもいいから、CO2の排出を減らせばいいわけです。
しかしそれって本当かなぁ?と思うところもあります。1kWhが、どこの原子力発電所でつくられたものか、どこの風力発電所でつくられたものか、末端の消費者は知る由もありません(最近はある程度選択できますが)。それでいいのかな、と気になるわけです。いまの社会のシステム、あるいはエネルギー政策も、「気にしない」ことを暗黙の前提として、形作られています。強いていえば、その1kWhを作る費用を最小化することが「正義」のように押し付けられています。
お金だって実は、同じ問題を孕んでいます。どんな1円でも1円であることが、お金の美しさでもあります。しかし最近では、マネーロンダリングの禁止のように、お金の出どころについて気にするようになってきました。目の前に1万円札があるからといって飛びついてはダメで、その出どころを気にしないといけない時代になってきています。
ということで、エネルギー政策でも、気候変動政策でも、あるいはもっと全般的な政策でも、1kWhとか、1t-CO2eqとか、さらには1円とかも、それぞれの「1」に付随する意味を、もう少し考えないといけないのだろうな…そしてそれぞれの「1」に付随する意味を記録する制度がこれから必要になってくるんだろうな…なんて思っています。まぁそれこそブロックチェインってやつなんでしょうが。
2019年9月29日
一昨年度、昨年度と委員として関わらせていただいた「地下水マネジメント」の検討成果が、「地下水マネジメントの手順書」として内閣官房水循環政策本部より公表されました。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/mizu_junkan/tikasui_management/tejunsho.html
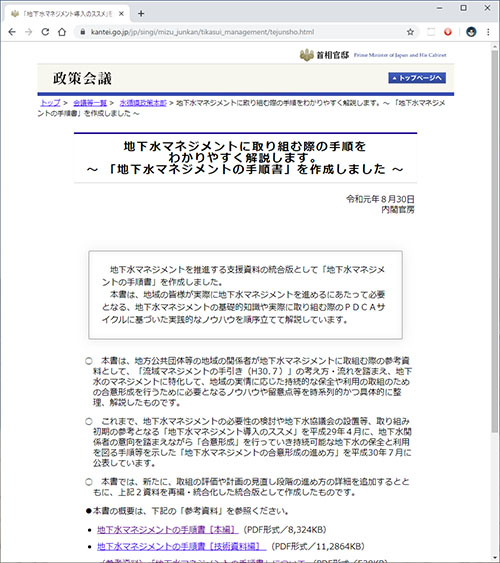
地下水の利用って高度経済成長の頃は、工業利用で汲み上げすぎて地盤沈下を引き起こすというパターンが多かったようですが、さすがにそういうことはずいぶん減ってきたようです。しかし最近はペットボトルの水がよく売れるようになって、飲料を生産するために汲み上げるニーズが増えてきたようで、しかも上流のほうで汲み上げるものですから、下流のほうで地下水が涸れるんじゃないかという懸念もあるわけです。さらに環境管理という面でも、水循環を持続可能にすることは当然必要ですよね。
ということで、地下水のマネジメントをしないといけなくなってきているのですが、権利関係なども歴史的経緯があって複雑なため、ステークホルダーがうまいことやっていくためのガバナンスが重要になります。合意形成というやつですね。なのでワタクシが召喚されました。
結局、自治体レベルで動いてもらわないといけない(全国レベルで管理することではない)ので、こんな手順書というものを国が用意して、最終的には自治体がこれを参考にマネジメントを進めてもらうことを期待しています。目立った補助金がついてくるわけではないのですが、地下水の問題を抱えている、抱えていそうな自治体の職員・議員さんはぜひ参考にしてみてください。
そういえば5年ほど前に調査した福井県小浜市の地下水、最近はどんな感じかな?