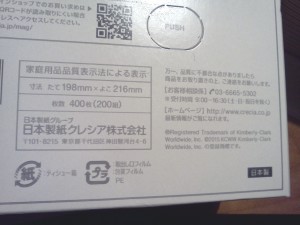2017年2月10日
洋上風力発電の地域合意形成についてはMIT在籍中から、かれこれ15年ほど、ウォッチしてきました。うまくいっている事例もあれば、ぜんぜんうまくいかない事例もあります。そんななかでも、特に地域に「愛されている」洋上風車である五島の浮体式洋上風力発電施設について、五島市役所再生可能エネルギー推進室への聞き取り調査とともに、視察してきました。
聞き取り調査などの専門的な内容は論文などに別途まとめるとして、今回は風車のご紹介。風車はこんなふうに、海のまんなかに建っています。

五島の風車は「浮体式」といって、実は足が海底に着いていません。細長い、巨大な電柱みたいな棒が海に浮いていて、流れていかないようにチェーンで碇に係留されています。海上に見える部分は鋼製ですが、海底の大部分はコンクリ製です。要は下水道などで使われる「土管」みたいなものですね。

視察した日は少し曇っていたのですが、逆にちょっと荘厳な雰囲気の写真を撮ることができました。写真の遠くには福江の街も見えます。
以前は椛島という島の沖合いに設置されていたのですが、昨年度末に、現在の福江島崎山沖へと移動したそうです。椛島は小さな離島ですので発電した電力を使い切れない問題があったそうですが、今度は五島列島で一番栄えている福江島の電力線へと接続されているので大丈夫なのでしょう。浮体式はこのように、比較的容易に移動できるというのがメリットかもしれませんね。現在の風車も、撤去せざるを得ない問題が発生したら、そのままどこかへ曳航すればいいわけですものね。

当日は、風車から一番近い崎山地区も訪問しました。上の写真のように、漁港の防波堤の向こうに、風車の翼を見ることができます。

また箕岳という五島らしい丘/山に登ったのですが、そこからは風車の位置関係がよくわかりました。上の写真のように、陸から、あまり離れている感じがしません(近くという感じでもないですが)。近くで漁船が操業しているのも見えました。実はこの風車、海中部分に付着物防止の塗装を敢えてしていないそうで、すでに大量に付着物(海草や貝でしょうか)がついており、そこに魚がたくさん集まってきているそうです。以前は魚が逃げるのではないかとみなさん恐れていましたが、実際に建ててみたらなんのことはない、逆に魚が集まってくることが判ったんですね。
さて、五島島内の移動、今回はレンタカーを利用しました。

見ての通り、電気自動車(三菱のi-MiEV)です。五島では、実は、エビッツ(EV&ITS)事業という名で電気自動車の利用をかなり本気で促進してきました。観光に電気自動車を使ってもらえるよう、EVの充電所もそれなりに整備されています。この事業、東大の生産研の鈴木高宏先生(当時)が長崎県に出向されていた頃に担当されたプロジェクトで、大学の先生が行政職員として現場で技術導入・社会実装したという、地域イノベーションの研究としてもとても興味深い事例なんですね。で、自分は、今回がはじめてのEV体験。最初はエンジン音がしないので非常にまごつきましたが、慣れると、けっこう、おもしろいです。回生ブレーキを効かせていかに航続距離を伸ばせるかという楽しみもありますし。もし五島にいらっしゃる機会があれば、是非EVレンタカー、体験してみてください。僕は「レンタカー椿」さんにお世話になりました。空港から貸し出し場所までの移動の間に、懇切丁寧に運転法を教えていただけます。
2016年4月26日
自分は日本の最近の大学改革の第一波の影響を受けた世代(40代前半)でありましょう。自分自身は、修士・博士課程は日本の大学システムとはほぼ絶縁状態でMITにおりましたので、影響は少なかったとはいえ、日本で教職についてからというもの、10年弱は時限プロジェクト予算での雇用を渡り歩く「特任」教員でありました。国立大学法人化以前はほぼあり得なかった、テニュアトラック以外の外部予算に依存する准教授職であったわけです。
それはいま振り返ってみればとても不安な生業であるわけですが、しかしまた、それはそれでやりがいのある仕事だったかもしれません。
というのも、自分の研究テーマがある程度、外部資金の拠出元の意向に左右されるので、自分が(当初)強い興味を持ってないことについても、生業のために研究することになります。それって研究者として悲惨、みたいな見方もあるでしょうが、逆に、タコツボ(いま風に言えばサイロ)に収まらずに、いろんな分野・業界の人々と交流できる環境を与えられたとも言えるでしょう。
で、思いついたのが、「イノベーションの順応的管理」ということば。
小職、最近まで文科省の「科学技術イノベーション政策のための科学(SciREX)」事業で特任雇用されてましたので、科学技術イノベーション政策なるものに焦点を当てた研究が期待されておりました。そんなこともあって、政府の「イノベーション万歳!」政策について批判的に検討しておりました。それでやはり出てくるのが、ロードマップという思考で、特に現政権になって経済産業省の影響力が強くなったせいか、計画文書にもよくあらわれます。
ロードマップとはなにかというと、これから10年なり20年なり先の目標を定めた上で、技術開発の動向を網羅的に補捉したうえで、いつまでにどのような要素技術を開発する必要があるかを特定して、順序だてて各要素に重点予算配分をしていく、という極めて美しい古典的OR思考に則る計画手法です。それはそれで美しいわけですが、現実に、そういう大規模プロジェクトが当初の目標を達成してきたかというと、無意味ではないにせよ、予定通りにはならないというのが、高度経済性長期における類似計画からの教訓ではなかったかと思います。
で、また話が逸れますが、別の環境政策の研究プロジェクトで、生態系管理とか里山里海とか、そういうことを研究している研究者さんたちともごいっしょすることがあったのですが、そのような業界では、旧来の計画法に対する反省が強いわけです。まだよくわからない自然のシステムを相手にしてるわけで、計画したって思い通りにいかないどころか、もっと悪い方向にいったりする。なので、バクチのような長期計画を決めるんじゃなくて、長期ビジョンを念頭に置きつつ、毎年のように更新されていく新しい知見を計画に反映する、計画を修正していくことのほうがダイジでしょ、というのが、環境政策業界の常識になりつつように思えます。
さて、イノベーション政策ですが、相変わらずロードマップ思考で、未来を見据えてそこに向けて要素技術を開発していくみたいなことが書かれているわけですが、どうなんでしょうね?技術開発の動向だって世界規模でコロコロと変化するわけで、日本だけで5年後10年後を見据えて計画をたてて実行しても、ガラパゴス一直線、ってやつでしょう。
だからこそ、環境政策の思考を取り入れて、イノベーション政策も順応的管理を前提にしたらどうでしょう。もちろんその傾向は出てきていて、研究者では「イノベーションのエコシステム」なんて物言いをする人も多くいます。でも、政策の文章を読む限りは昔の計画のパターンとあんまし違いないよナーと感じる限り。
ということで、「イノベーション政策の順応的管理」という思想が、科学技術イノベーション政策の現場に、必要なんじゃないかと思うところです。
で、こういう思考ができるのも、特任職を渡り歩いて、いろいろな分野の知識を吸収する機会があったからかな、とも思う次第です。
2015年12月30日
タイトル見てエロい内容だと思いました?
安心してください、エロくないです(ゴメンナサイ)。
先日、食卓で使うティッシュを間違えて2箱出してしまったのです。いずれもスコッティのぱっと見、同じ箱なのですが・・・なんとなく眺めていたところ・・・

大きさがぜんぜん違うじゃん!
幅はほぼ同じですが、高さがかなり違います。「安売用に中身減らしてんじゃねぇの?」と疑ったものの、いずれも400枚(200組)との表記あり。
どうなってんだろ?とよく見てみると、片方の裏面には「(c) 2011 KCWW Kimberly-Clark Worldwide…」、もう片方には「(c) 2015 KCWW Kimberly-Clark Worldwide… 」と書いてある。
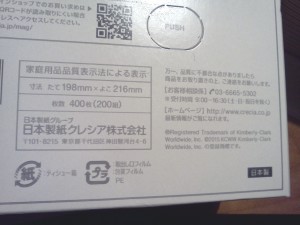
なるほど、どうやら片方は、震災後のどこかで備蓄用に買っておいたティッシュだったらしい。もう片方は最近買ったティッシュ、ということらしい。もちろん、最近買ったほうがコンパクト。
ということでサイズ(外寸)を計測してみると・・・
2011(?)版:
W 236 x D 117 x H 55 = 1518660 mm^2
2015版:
W 227 x D 117 x H 45 = 1195155 mm^2
ってことで容積にして21%の減容!
すごいですね。輸送にかかるコスト、CO2の排出、その他諸々をずいぶん節約できてますね。
こういうのこそイノベーションってやつなんじゃないか、ってことで、「ティッシュ・イノベーション!」って叫びたくなってしまいました。
もちろん、「イノベーションなら、そもそも木質パルプを使わなくてもいい、あるいは再利用できるようにするくらいの革新が必要なんだ!」と力説される方もいらっしゃるでしょう。
しかし、何はともあれ、わずか数年で20%の減容っていう企業努力は、イノベーション!と称えてもいいんじゃないかなぁ、と思うわけでして。